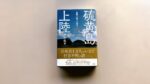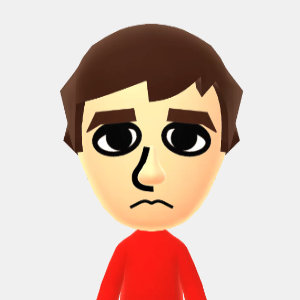【書評】圧倒的な成果を生み出す「劇薬」の仕事術【レビュー】
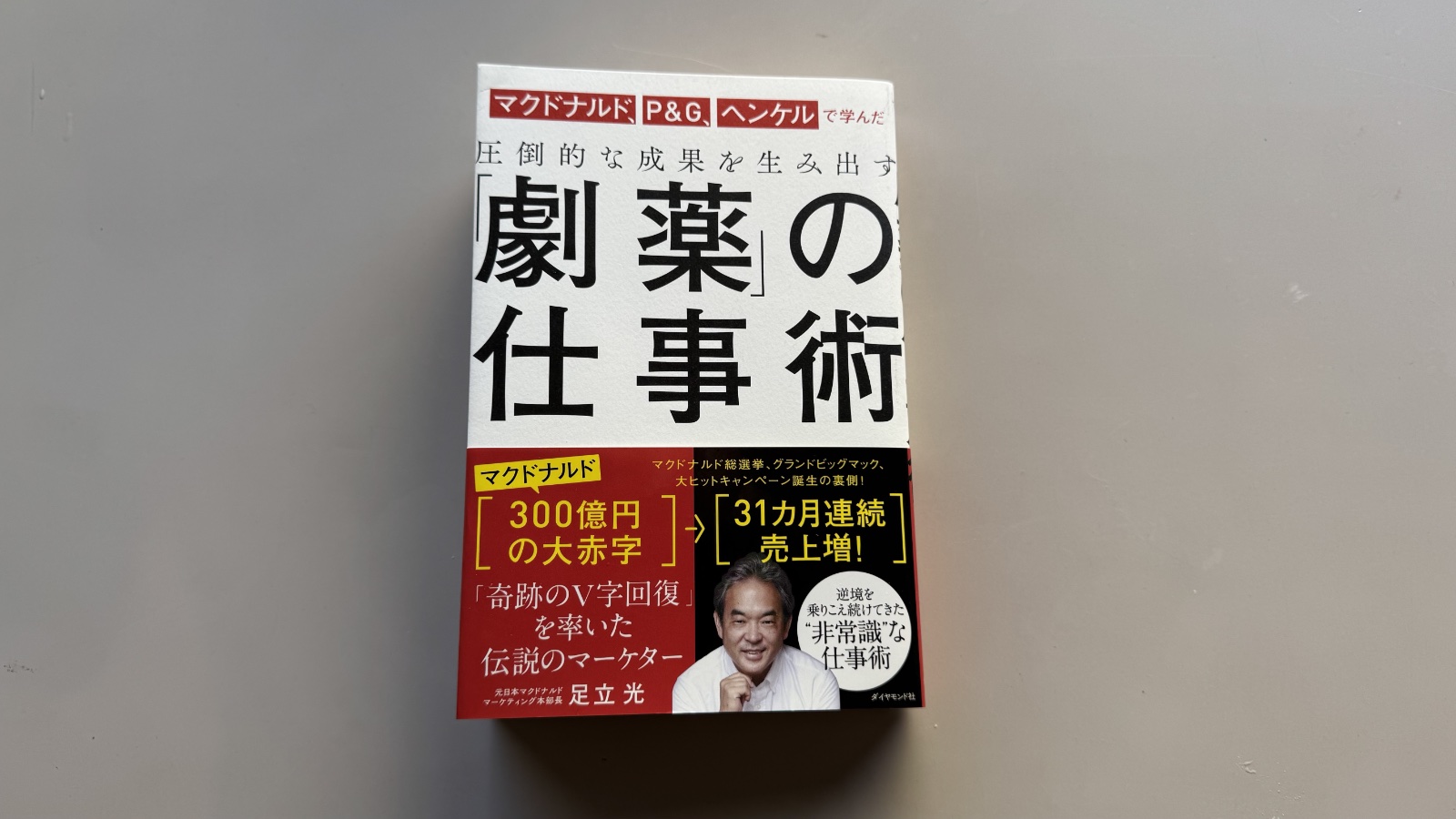
著者は足立光さん。
P&Gジャパン、ブーズ・アレン・ハミルトン(政府系コンサルティング会社)、ローランドベルガー、シュワルツコフヘンケル、ワールド、などを経て日本マクドナルド・マーケティング本部長に。
数々の経験を元に、当時窮地にあった日本マクドナルドを救った男。
以下気になったフレーズなどを紹介。
Love over Hate
足立さんがマクドナルドのマーケティング責任者になった当初、当時マクドナルドは食品衛生管理の不祥事などで業績が右肩下がりであった。
そんなマクドナルドで足立さんが悪い評判を払拭するために実施した施策の根本の考え方。
それが「Love over Hate」。
悪い評判に対して、1つ1つ細かく誠実に対応するのではなく、悪い評判をマクドナルドという会社に期待されている良いニュースを継続的に投下して上書きすることで、会社のイメージを良くしていくという戦略。
広告より広報。第三者に発信してもらうきっかけを与える。
Love over Hateの考えを実践するには、自社からの一方的な発信では不十分。
楽しそうなニュースでファンや顧客にきっかけを与え、情報を受け取った方に発信してもらう。
そうすることで企業イメージは好転していく。
モノ消費ではなくコト消費を訴求することで、顧客やファンはより楽しんでくれる。
数字で測れない仕事はしない。
当時マクドナルドでは、施策をやったらやりっぱなしになっていたらしい。
そうではなく、きちんと施策を振り返り、何が良くて何がだめだったのか、次に活かすことが重要、という考え。そのためには施策をきちんと計測できないといけないし、それを定量的に評価しないといけない。
日本の人事制度にも触れている。
日本は評価が曖昧で、多くの人が「まぁまぁ仕事ができる」という評価に落ち着きやすい。
足立さんはワールド入社後、経営立て直しのためにリストラを担当することもあった模様。
その際、該当の人の評価がどこに位置しているのかを明確にできないと、リストラ対象を絞り込むのも大変になってしまう。誰が仕事ができて評価されるべきなのかを見定めることは会社の成長そのものに大きく影響する。
仕事を共にする人をパートナーとして尊重する。
広告代理店と一緒に仕事をすることが多いが、その人たちを「業者」扱いしない。
一緒に仕事を共にするパートナーとして、「どうすれば良くなるか」のアイデアを出してもらいやすい環境づくりが大切。信頼してもらうために、サプライヤーや広告代理店、店舗のスタッフなどいろんなステークホルダーの声を聞きに自ら向かう。
求められているものを見定め、提供する。
マクドナルドは、窮地の際に、野菜をたくさん取れるベジタブルバーガーを訴求していたりした模様。
それは、会社のイメージが悪かったので、健康訴求を重視した企画らしい。
しかし、顧客やファンはそれを求めているのか?マクドナルドに求めているのは、カロリー高くて健康には悪いけど、「背徳感」を感じながら食べたいものを食べるということではないか?
だったらそこのニーズを満たしていこうよ、という考え。
安売りはしない。レギュラー商品の売り方を変える。
マクドナルドは、業績下降前はデフレの寵児として100円マックなど、安さ訴求で勝負できていたが、そういう施策は企業ブランドを毀損しかねない。安く売るのではなく、付加価値をつけて高く売ることを考える。
特別キャンペーンの商品は、一時的には売上に貢献するが、コケたら大きく売上が下がるし、ずっと売り続ける商品でもないので効果も限定的になりがち。
ビッグマックやフィレオフィッシュなど、レギュラー品について、ファンが楽しんでもらえるような施策を考える。
足立さん在籍時にマクドナルドが行った施策の数々
- マクドナルド総選挙
- ヘーホンホヘホハイ
- 森永ミルクキャラメル味のシェイク
- ポケモンGOとのタイアップ
- 名前募集バーガー
- マックvsマクド
- 絶対美味しくないと叫ばせる「マックチョコポテト」
「劇薬の仕事術」は「自分のミッション」と「仕事の責任」への姿勢の話のように感じた。
読んだ感想として、足立さんのスーパーマンぶりが光る様々なエピソードではあった。
ただ、足立さん自身は、大変だとか嫌とかいうより、自分の人生に課せられたミッションとして「自分のまわりの人たちを幸せにすること」を掲げており、そうなるためのアクションをとっていただけのように感じる。
そのためには、大胆な変化をしないといけないし、それに伴う意識変化も促す必要がある。
さらにそうするためには、自分のプレゼンスを高めて話を聞いてもらわないといけないので、早々に結果を出す必要がある。
そんな状態であったので、おのずと他の人ができないような、働き方だったりアクションを実行できたのかなと思う。
逆に言えば、結果を出せていない人は、「上司が」とか「会社が」とか、言い訳を言いながら生きており、真摯に仕事というものに向き合えていないとも言える。
「劇薬」たる仕事の進め方は、相当自分に対して厳しくないとできない働き方ではあると思いつつも、課題や目的に対して、何が課題でどういうアクションを取るべきか考え、成果を最大化させるために、関係する人と協力しながら、忖度せずに前進することが重要、というメッセージだと感じました。
真に成果を出せる人は、こういう熱量を持っているんだな、と思わされる一冊でした。