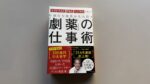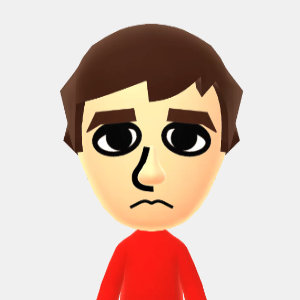【書評】硫黄島上陸〜友軍ハ地下ニ在リ【レビュー】
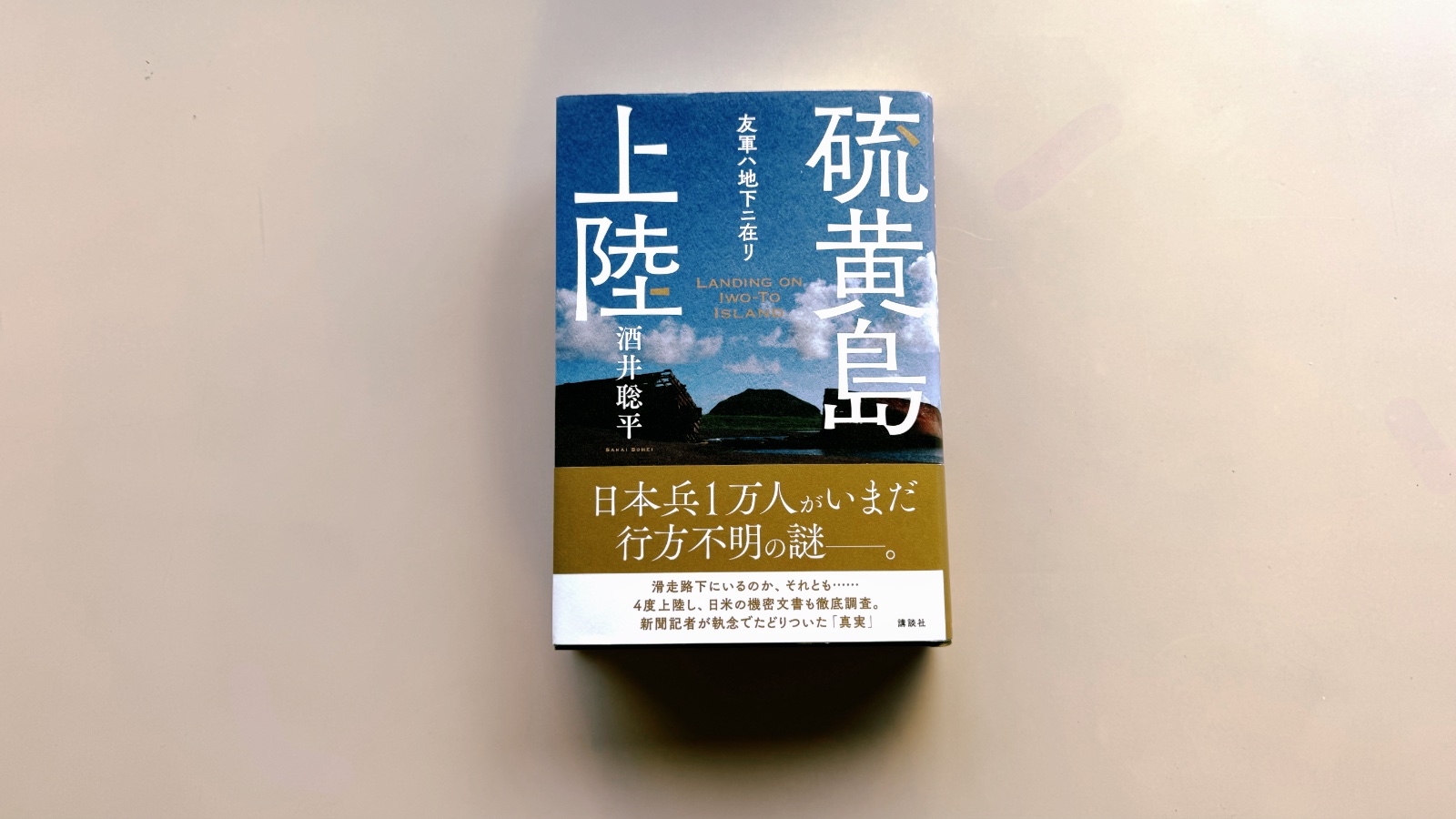
硫黄島上陸〜友軍ハ地下ニ在リ、という本を読んだ。
先日コーチャンフォー若葉台店という多摩ニュータウン方面にある広大な本屋さんでふと目にとまって購入した本。
小説や文庫というより、リアルな史実のようなものに少し興味が出て、手に取ってみた、くらいの流れ。ちまちま読み進めてた感じなので、読了まで2週間くらいかかった。
ハードカバーの本で1,500円。著者は北海道の新聞社に勤める酒井聡平という方。
この本、「2024年度山本美香記念国際ジャーナリスト賞」という賞も受賞しているみたい。(この賞がどの程度の認知や権威があるものかはわからんけど。)
以下気になったことをまとめておく。
硫黄島での激戦で命を落とした兵士3万人のうち、1万人分の遺骨が見つかっていないミステリー。
硫黄島での激戦で命を落とした兵士3万人のうち、1万人分の遺骨が見つかっていない。
これはミステリーではあるが、作者は国の報告書などを取り寄せて、事実を探し求めていく。
語られた可能性は以下のようなもの。
- 戦いの後の、島のアメリカ軍基地化するにあたり、日本の建設会社に整備を依頼、その会社が発見した遺骨を埋葬した可能性。
- アメリカ軍が持ち去った可能性。
- 風化の可能性。
- 飛行場整備の際、そこにあった地下壕もろとも埋めてしまった可能性。
- 北硫黄島に船で脱出を試みたが、辿り着けなかった可能性(硫黄島と北硫黄島の間は72kmもある)
日本とアメリカ間の核の配置をめぐる推察あり。
硫黄島は戦後も日本の領土ではあったが、実際はアメリカ軍の統治下にあり、戦前硫黄島に住んでいた人は結局、帰島することはできなかった。
それは硫黄島が、軍の訓練場として機能させるのにちょうど良かったから。
また、軍事的な拠点として、核の装備を保管するのにちょうど良かったというような仮説も展開される。
確実は情報ではなさそうだが、それにより、元島民は帰島することができなかったし、遺骨収集の活動も時期が限定され、任意のタイミングで行うことができなかった理由なのでは、といった背景も語られる。
遺骨の収集活動の継続させることの難しさ。
遺族や硫黄島での戦いに関係した方々が高齢化し、お亡くなりにもなるので、それを継続する強い意志を持つ人が少なくなっていく。継続させるためには日本政府のサポートも必要になってくる。
そういう外部要因で継続が難しくなってくる現状もあるみたい。
実際、新たな遺骨見つけるとなると、硫黄島の空港地下を掘り起こさしないといけないだろうし、コスト面含め様々なことが障壁になってきそう。また遺骨の風化などもあり、見つかる保証もない。
遺族の心情的には継続したいのはやまやまだろうが、一定の線引きも必要という、感情の落とし所として難しいものがありそう。
遺骨の収集活動にあたりながら、それに携わる人との繋がりも強くなっていく。
本の後半では、遺骨収集に一緒に携わった「仲間」の方々とのエピソードも。
近くの父島、母島の通信所の通信士の子孫の方々は継続的に遺骨収集活動に携わっており、その方々の姿勢や人となりを通して、遺骨収集活動の難しさなどを浮き彫りにしていく。
遺骨の状況などから見えるのは、戦争の悲惨さ。
遺骨がどのような状況で発見されたか、ということも語られるが、どうにも恐ろしい状況。
硫黄島の兵士は日本軍の救援が来ると信じて待っていたが、結局は国から見捨てられたような状態。
硫黄島から父島の通信所に送られたメッセージは辞世の言葉、感謝の言葉、家族を心配する言葉などがあり、どれを見てもやりきれない。
硫黄島そのものは火山島であり、地形変化も激しい。
地下壕で数多くの遺骨は発見されているようだが、地熱の苦しさ、あと、硫黄島には川が流れていないので水の確保も相当難しかったと思われる。そんな中、国を思って戦い、耐えた兵士の方々を思うと、せめて遺骨だけでも日本に戻してあげたいという気持ちは重々わかる。
だけど、上記のような現実問題として難しい面もある。
遺骨の全回収は現実的でないとしても、硫黄島の戦後から遺骨収集に携わった人の活動や想いを記録として残されたという点で、この本には大きい意味があるのかなと感じた。