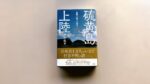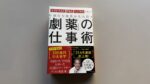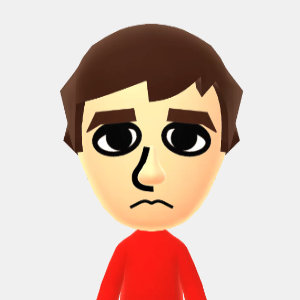【書評】もしも高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら【レビュー】
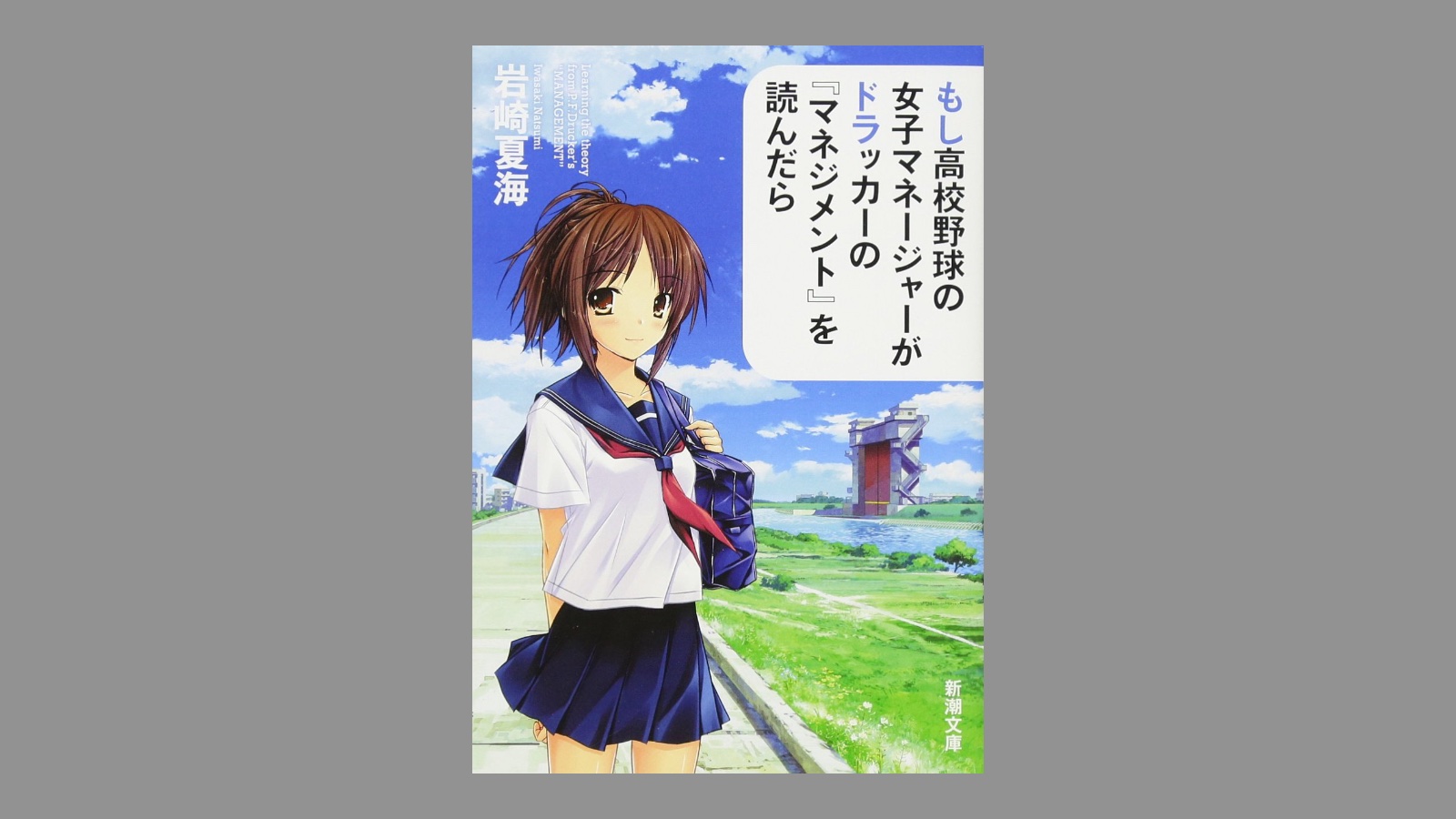
「もしも高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」を読んでみた。
発行は平成27年ということだから2015年の発行の本なので、結構昔の本。
そしてベストセラー本で有名な本ですよね。
もちろん自分も本の名前はよく耳にしていたのだけど、何となくそのままスルーしてた。
最近本をよく読むようになったし、昔のベストセラーだし押さえておくか、ってことで例によってAmazonの中古本で購入。ざっと感想を書いておく。
とにかく読みやすい。感動ストーリーもの。
結局読み始めてから読み終わるまでは、2日間くらい。時間にすると、3時間くらいで読んだかなという気持ち。ページ数は300ページくらい。
一文一文が長すぎないので、理解しやすく、スッと入ってくる。
視点も主人公の女の子のみなみさんで一貫しており、ストーリーも「甲子園に出るためにある課題を解決していく」ということで明快シンプル。
お話の迷子になることがない。
野球部、マネージャー、地域、高校野球会を巻き込んで甲子園を目指すお話。
主な登場人物は、
- 主人公のみなみ(マネージャー)
- 元々は野球にものすごい情熱を持っていたが選手と距離を置く監督
- 先の試合で監督に交代させられたことを根に持つピッチャー
- 野球はうまくないが起業のための勉強と思ってチームに入った裏マネージャーみたいな人
- 病気で入院中、お見舞い面談でチームの声を聞く元マネージャー(みなみの幼馴染)
- 内気だが秀才肌のもう一人のマネージャー
- みなみの活動に影響を受けた吹奏楽部のキャプテン
- 緊張でここぞでミスをしてしまいがちなショートの選手
特に、病気で、ベットからあまり動けない元マネージャーとのやりとりと、そのやりとり踏まえた彼女の変化は印象的。
またそれぞれのメンバー一芸を持っているので、個性が立っているのも良いところ。
ドラッカー「マネジメント」を踏まえた数々の変革が痛快。
そういった個性的な面々が、各々が持つ一芸を生かして、課題を解決していくわけだが、その様が痛快。
以下、具体的な実践項目を挙げておく。
- 誰を喜ばすべきか、顧客は誰かを明確にする。
- 練習そのものを楽しくする。チーム間で競争意識を芽生えさせ、成長具合を可視化する。
- 顧客とウィンウィンの関係を構築する。
- 選手、監督が抱える悩みや思っていることを打ち明けてもらう場を作る。
- 関係者に役割と責任を与えて任せる。
- 独自の戦略を打ち立てる。(ノーバント、ノーボール作戦)
- マネジメントできる人数規模を絞る。広げすぎない。
これらを順次、選手や監督の意識や行動に浸透させていくことで、元々持っていた特性や才能が開花。
野球部の監督も選手も実は元々有能な素質があったというご都合主義はあるが、そんなことは些細な問題。
ドラッカー「マネジメント」の内容は薄め。迷った際に立ち返るバイブルのような扱いとして存在。
ぶっちゃけ、この本でドラッカーの「マネジメント」の内容全てを理解できるかというとそういうわけでもない。ドラッカーの理論が網羅されているということはなく、「マネジメントという本の何ページにこのように書いてある」という感じで、みなみが困った際に、「マネジメント」のとあるページを思い出して、それを実践してみた、といった扱いが続く。
ただ、あらゆるアクションがストーリーの中で展開されるので、理解に繋がりやすい気はした。
体系的に理解するというより、考えの根幹のイメージを共有できるって感じかな。
自己啓発本?とかって構えず、感動小説をサラッと読む、くらいがちょうど良い向き合い方。
最初に言ったように、この本、スラスラと読める。本当に読みやすい。
発生する課題をドラッカーのマネジメントに基づいて解決していくという特徴こそあれ、それが全面に出てきすぎることもなく、あくまでツールとして使われている感じ。
野球部やそれを取り巻く面々の個性もはっきりしており、各々が自分の強みを生かして、活躍する様を見ると、「自分の人生でもこのような考えを取り入れていかねば」という気持ちになる。
特に「人の声を聞く」「人の特性を活かす」「顧客は誰で顧客の求めるものは何か」。
このあたりのお話はマネジメントの基本ではあると思いつつもこれまで自分自身十分できてなかったかも、という反省にも繋がったし、ストーリー仕立てになっていることで、自分ごとに置き換えて考えやすいというのもこの本のメリットかもしれないですね。